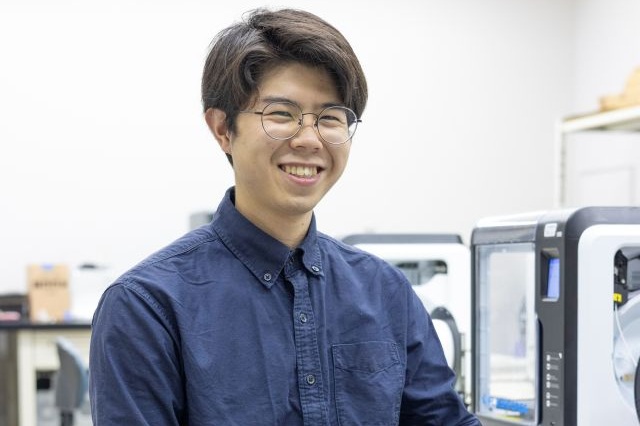学部・大学院
機械システム学系
先進製造コース
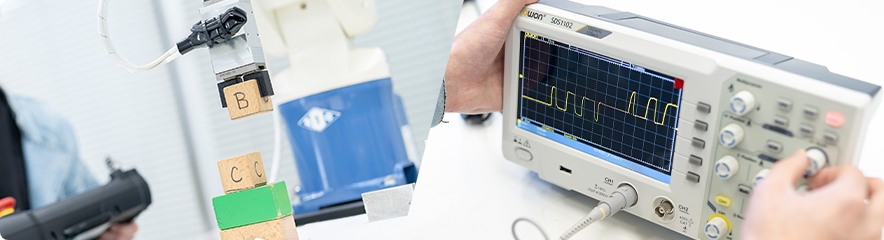
コース紹介動画
学びの特徴
-
構造・機能性材料の授業で、構造用材料・機能性材料の性質を学ぶ。
-
機械保全技術Iの授業で、国家技能士資格である機械保全技能士の資格試験対策を学ぶ。
-
構造・伝熱シミュレーションの授業で、機械設計に関するシミュレーション解析の知識や活用技術を学ぶ。
ピックアップ
カリキュラム
-
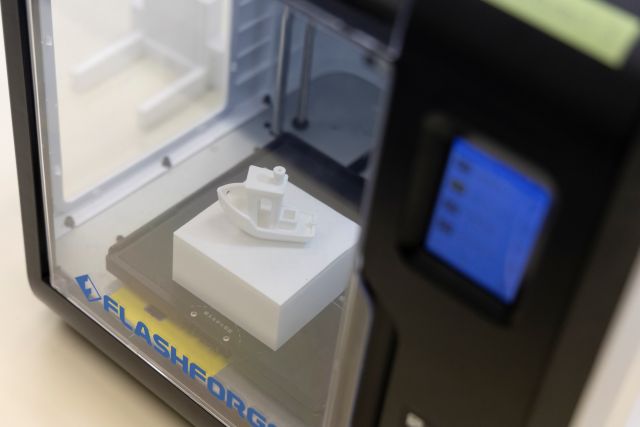
立体造形
立体を構成する概念や造形要素の知識と技法を学びます。3次元CADによるモデリングから3Dプリンタによる造形までの演習を通して、発想カ・表現力・造形力・構成力を養うとともに、基本的な加工技術を身に付けます。
-
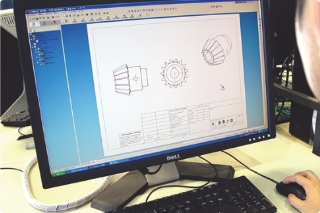
機械製図
ものづくりでは、さまざまなアイデアを機械や器具として具現化するとともに、実際に製作するためには、その概念を正確に情報伝達する図面が必要です。講義と演習を通し、製図の基礎から製作図面を仕上げる方法を学びます。
-

自動加工技術
現代の生産体制は著しく進歩しています。最新のNC加工、CAD/CAMのシステムの原理を理解し、演習を含めてNCプログラムの基本的な作成技術を学び、ものづくりにおける生産の省力化や無人化技術を身に付けます。
4年間の学び(専門科目)
共通科目
1年次
■工学共通科目 技術社会の基礎
工学概論/電気工学基礎/地球環境とエネルギー/くらしの科学技術/ユニバーサルデザイン/ロボティクス概論
■工学共通科目 コンピュータの利活用
コンピュータリテラシ/コンピュータプログラミング基礎
■工学基礎総合・実験科目
工学基礎ゼミI・Ⅱ/工学基礎実験Ⅰ・Ⅱ
2年次
■工学共通科目 技術社会の基礎
技術英語/地域防災工学/身体の機能や構造の計測と解析
■工学共通科目 コンピュータの利活用
入門CAD/IotとAIの基礎
■技術者教養科目
イノベーターとビジネス構築力/技術者倫理
3年次
■工学共通科目 技術社会の基礎
品質管理
■工学共通科目 コンピュータの利活用
データサイエンス
■技術者教養科目
知的財産法/ものづくりのための経営・戦略の基礎
※カリキュラムは変更になる場合があります。
コース専門科目
1年次
■機械科学の基礎
機械の要素と機構
2年次
■機械科学の基礎
機械工作法/機械の力学Ⅰ・Ⅱ/材料力学/計測工学
■機械システムの基礎
機械製図/工業材料/シミュレーション技術の基礎/電気電子工学Ⅰ・Ⅱ/サーピスロボティクス
■コース総合・実験科目
先進製造コースゼミⅠ・Ⅱ/先進製造コース実験Ⅰ・Ⅱ
3年次
■先進製造の基礎
機械CAD/テクニカルイラストレーション/自動加工技術/構造・機能性材料/機械保全技術Ⅰ・Ⅱ
■先進製造の応用と発展
メカトロニクス/立体造形/構造・伝熱シミュレーション/熱・流体シミュレーション/組込みシステム
■コース総合・実験科目
先進製造コースゼミⅢ・Ⅳ/先進製造コース実験Ⅲ・Ⅳ
4年次
■コース総合・実験科目
先進製造コースゼミⅤ・Ⅵ/卒業研究
※カリキュラムは変更になる場合があります。
資格
-
取得できるもの
- 高等学校教諭一種免許状(工業) ※教職課程履修者
-
受験資格が得られるもの
- 品質管理検定
- テクニカルイラストレーション技能士
- 機械保全技能士
- 機械検査技能士
- 固体力学分野の有限要素法解析技術者
- 振動分野の有限要素法解析技術者
- 熱流体力学分野の有限要素法解析技術者
就職実績
-
新潟工科大学を卒業後、
先輩たちはさまざまな分野で活躍しています。主な卒業後の進路
機械等の開発・製造技術者、機械保全技術者 など