
電子情報学系数理論理学研究室
松田 直祐助教
Matsuda Naosuke
通説として正しいとされている事象も疑ってみる、
その視点から新しい研究が生まれる

研究の内容を教えてください。
数理論理学といって、正しさを示すために証明という議論があります。それを形式化といって、コンピュータで扱えるような対象に落とし込む(コンピュータ言語化)理論の研究をしています。数学の証明というのは、簡単な正しい主張から議論を重ね、より複雑な主張を証明していきます。応用例としては、数学の証明を機械の中でチェックしたり、その証明を半自動的にコンピュータで作ったりというようなことに使われる学問です。簡単な主張から、より複雑な主張を導く証明の過程を、数学界では推論といいます。証明の仕方には流儀があって、そのひとつに直観主義論理というものがあります。これまで正しいとされてきた推論を一部認めない制限のある考え方です。または一般的に正しいと認められてきた古典論理というのも存在します。この2つの論理の間にどれだけ差があるのかというのが、私が今、最も興味を持っているテーマです。

研究室の学生は、どのような研究をすることになりますか
私の研究室では実験というのはないので、研究を手伝ってもらうというようなことは特にありません。せっかくの大学生活なので、自分の好きなことを自由に研究してもらいたいと考えています。学生の話を聞いていると、AIに関連する数学に興味のある学生が多いようです。私も一緒に勉強しながら研究を進めていきたいと思います。前期に数学系の授業を2つ受け持ったのですが、興味を持ってくれる何人かの学生に会うことができました。
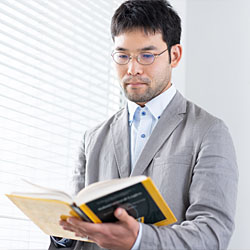
研究を通して伝えたい事は何ですか
数学の科学的議論を行う上で、物事を論理的に伝える力は重要です。それ以上に、日々の生活の中でも重要な力ではないかと思います。ある事柄について自分の主張を人に説明するために、どんな議論をしてどんな説明をすれば相手に伝わるのかと考える力を身につけてもらいたいと思っています。
研究室では技術的なことではなく、理論の応用分野の土台になるところを学んでもらいます。そういった意味では、社会に出てからも、どんな業種にも対応できる学問ではないかと思います
。
学生に期待していることはありますか
学んでいく上で意識してほしいのは、正しいと知られていることも疑ってかかりましょうということです。1冊の教科書にも100か所以上は間違いが書いてあるものだと思ってくださいと、授業では最初に言っています。正しいとされている定理の結果も鵜呑みにするのではなく、正しさを自分で確認してほしい。既知の結果が間違っていて、そこから新しい研究に繋がることもあります。実際、私も過去の論文に誤りがあって、そこを改良してやり直したものもあります。すでに知られているようなことでも疑問を持って勉強してほしいです。そうすることで、いろいろなところに研究の芽が見つかるはずです。
| 受験生の皆さんへ | やりたいことが明確な人は、将来のビジョンに合った選択をすればいいと思いますが、何をすればいいかわからない人は、「今、楽しそうなこと」を選んだらいいと思います。大学で学んだものとは関係ない人生を、その後選択してもいいわけですから。私自身、将来の夢もなく大学進学しました。その時にやりたいことに飛びついてもいいのではないでしょうか。 |
|---|---|
| 研究に関する情報 | 教員紹介 研究分野・テーマ 研究業績等一覧 |

